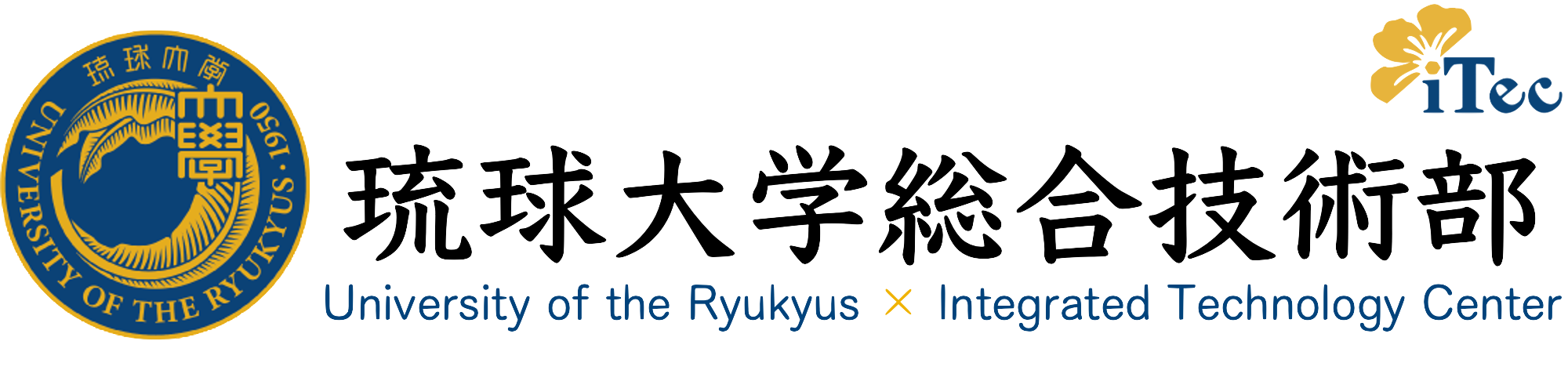2025年1月23日から1月30日までの1週間にわたって研究基盤EXPO2025(主催:研究基盤協議会 共催:文部科学省)が開催されました。
研究基盤EXPOは、研究基盤に関わる多様なステークホルダーによるイベントを集約し、効果的に情報発信・情報収集する場として毎年開催されているイベントです。
研究基盤EXPO2025の2日目は岡山大学を会場に「共創の場」シンポジウムが開かれ、「ヘリウム未来革命:資源循環で築くサステナブルジャパン」をテーマに大学等から6名が登壇し、学外と連携したヘリウムリサイクルに関わる活動報告や議論が行なわれました。
ヘリウムはNMR装置の超伝導電磁石の冷媒、物性物理の実験や開発など様々な研究活動に欠かせない資源です。しかし日本国内では産出されず、海外からの輸入に頼らざるをえないところ、これまで幾度も世界的な供給不足に陥っています。そのような社会情勢の中、特に液体ヘリウム(-269℃)についてはガス化したヘリウムを回収し再液化するリサイクルが大学等の限られた範囲内で行われてきました。
近年では、このヘリウムリサイクルの取り組みを、大学全体や学外の研究機関へと広げようとする動きが活発になっています。こうした取り組みを進めるには、ヘリウムの再利用に関する知識や技術、さらに研究機関同士のネットワークの活用が不可欠です。本シンポジウムでは、これらの要素に先進的に取り組んでいる複数の大学から、その実例が紹介されました。
本学からは総合技術部の宗本久弥氏が登壇し、沖縄で軌道に乗った液体ヘリウムリサイクル実施状況が報告されました。本学は県内唯一の大型なヘリウム液化装置を有し、学外機器共用として沖縄科学技術大学院大学(OIST)・沖縄県工業技術センター・沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの3機関と連携しています。各機関から回収されたヘリウムガスは研究基盤統括センター極低温施設に受け入れ、再液化し送り出されています。
パネルディスカッションでは、施設維持管理に関わる技術の継承や後継者育成の重要性について、経営層に伝わるように発信することの課題共有がなされました。また宗本氏からは、「次なる供給危機に備えて今からヘリウム回収の貯蔵・輸送手段を準備しておくことの重要性と、できることから始め徐々に各施設にあった方法に改良していければよいのでは」等の意見がありました。
参考
研究基盤EXPO2025
https://www.jcore2023.jp/activities/expo/expo2025/