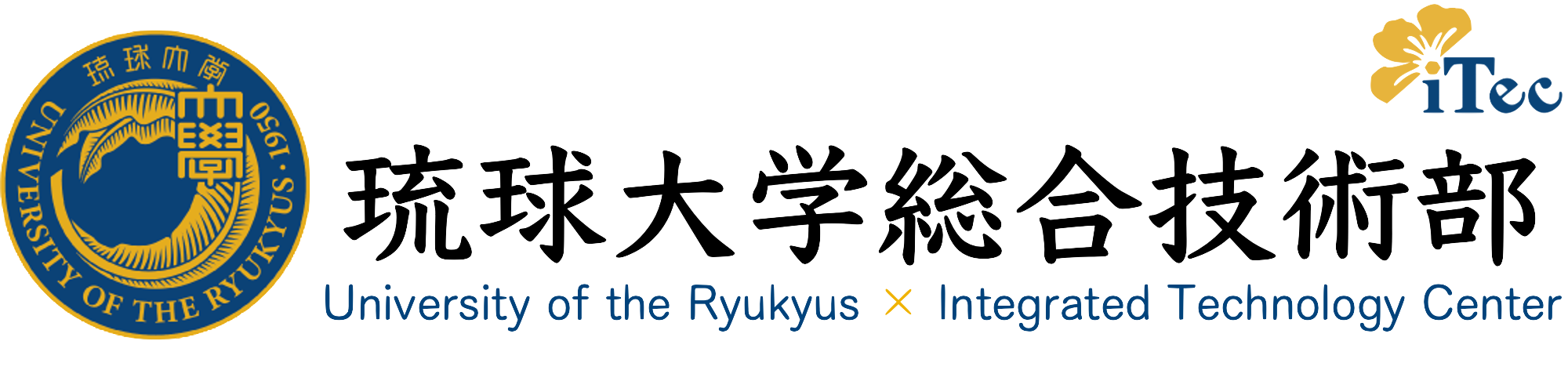2023年10月1日に琉球大学総合技術部が設置されて以降、全学的な組織として琉球大学の教育研究を技術的側面から支えるとともに、地域社会に対しても積極的に技術教育を提供しています。設置以前から技術職員は学内で活躍していましたが、その活動状況は各現場でのみ把握され、部局が異なると知る機会が限られていました。総合技術部の設置により、技術職員の活動が組織的に整理され、発信も行われるようになったことで、学内外からその取り組みがより見えやすくなり、技術支援活動への理解の深化が期待されています。
2024年度からは業績評価もスタートしています。技術職員の業務は多岐にわたるため、単一の基準で評価することは容易ではありませんが、異なる分野や業務の視点から相互チェックを行い、評価の精度を高めていく方針です。評価制度の導入により、技術職員一人ひとりの業務の質向上とモチベーションの向上が図られ、総合技術部全体のポテンシャルをさらに高めていけるものと考えています。
また、総合技術部の設置によって異分野の技術習得がより容易になったことは大きなメリットです。各分野の専門技術を他分野の技術職員に相互にレクチャーすることで、専門性の幅が広がっています。もちろん技術の深度には違いがありますが、もともと技術者としての素養を持っているため、習得度は一般的な初学者とは異なるレベルに達しているはずです。さらに時間をかけることで、複数分野の技術を高度に習得する技術職員が現れることも期待されます。異なる専門性が融合することで新しい価値が生まれることは、バイオ発電、医療ロボット、スマート農業、サステナブル建築など、多くの実例が示している通りです。今後、学際的な研究プロジェクトにおいても、こうした幅広い知見を持つ技術職員が大いに活躍することが期待できるだけでなく、地域社会や産業界における実用的課題の解決にも寄与する可能性を秘めており、外部機関との協働や技術交流の機会も今後さらに増えていくものと思われます。
話が少し逸れましたが、琉球大学総合技術部は18の業務グループで構成され、それぞれの専門性を活かした技術をサービスとして提供しています。基本的には学内の各部局に派遣され、研究と教育を支援するスタイルをとっています。また、研究基盤統括センターが保有する多数の研究機器の保守管理も担っています。あまり知られていませんが、研究廃液の処理といった業務も日常的に行っており、これには相当な体力が求められます。
人数も時間も限られていますが、日常業務に加えて、さまざまな技術的課題の解決に向けて日々努力を重ねている技術者集団です。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
2025/6 更新